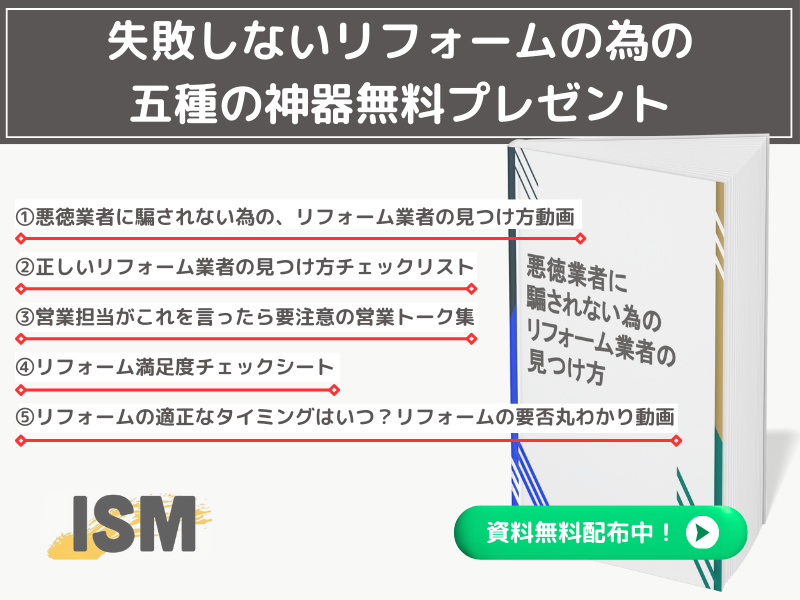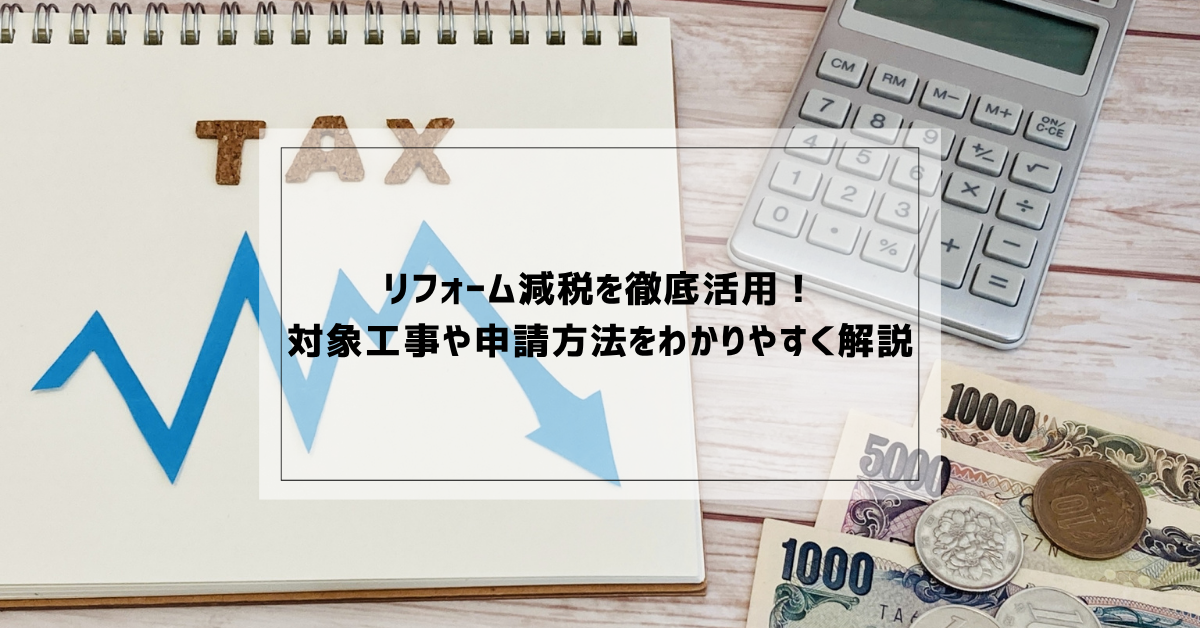マイホームをより快適に、長く住み続けるために、リフォームを検討している方は多いでしょう。しかし、リフォームにはまとまった費用がかかるため、資金計画を慎重に立てる必要があります。
そんなときに知っておきたいのが、国の「リフォーム減税制度」です。条件を満たせば、所得税や固定資産税などの負担を軽減できるため、リフォームを検討する家庭にとってメリットの大きい仕組みです。
しかし、「どの工事が対象になるの?」「どんな申請が必要?」と、制度の全体像がわかりにくいと感じる人も少なくありません。この記事では、2025年最新版のリフォーム減税制度について、対象工事や申請方法、併用ルールまでをわかりやすく解説します。
「リフォームをするなら、少しでもお得にしたい」という方は、ぜひ最後までチェックしてください。
目次
知っておくべき!リフォーム減税制度について解説

リフォーム減税とは?
リフォーム減税とは、住宅の改修・改築を行った際に、一定の条件を満たすことで所得税や固定資産税などの税金が軽減される制度です。たとえば、省エネリフォームやバリアフリー化、耐震改修などの工事を行った場合、その費用に応じて控除を受けられることがあります。
個人の負担軽減だけでなく、長く暮らせる住まい作り、環境負荷の低減(省エネ化)、そして高齢者や障がいを持つ家族も安心して暮らせるバリアフリー化といった、社会的なニーズに応えるための住宅政策の一環として機能しています。
リフォーム減税制度の目的と種類
リフォーム減税制度には、目的に応じていくつかの種類があります。主なものは次の通りです。
- 住宅ローンを利用した場合の所得税控除(住宅ローン型)
- ローンを利用しない場合の投資型減税
- 固定資産税の軽減措置
- 贈与税の非課税措置(親からの資金援助)
それぞれ控除額や対象工事の範囲、申請手続きが異なります。自分のリフォーム計画に合う制度を選ぶためには、制度の内容を正しく理解することが大切です。
2025年の適用期限と変更点
2025年現在、リフォーム減税制度には期限付きの特例措置が多く存在します。特に、省エネ改修やバリアフリー改修などに関しては、住宅ローン控除や投資型減税の適用期限が延長されています。
たとえば、「住宅ローン控除(リフォーム)」は2025年12月31日までに入居した場合に適用可能です。また、省エネ改修の対象となる基準が見直され、より高い断熱性能や省エネ基準を満たす必要があります。
このように毎年内容が更新されるため、「昨年と同じだろう」と思い込んで申請してしまうと、控除対象外になることもあります。リフォームを検討する際は、最新の公表資料に基づいて計画を立てることが重要です。
【目的別】リフォーム減税制度の種類と対象工事

リフォーム減税制度は、工事の目的や資金の出どころによって複数の種類があります。ここでは、代表的な制度と、その対象となる工事内容を紹介します。
3つの減税制度の概要は以下の通りです。
| 制度の種類 | 主な対象工事 | 控除内容 | お得になる目安 |
| 住宅ローン型減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除) | 耐震改修工事 バリアフリー改修工事 省エネ改修工事 その他工事(居室、調理室、浴室、トイレなどの床面積を増やす増改築・修繕等) | 年末ローン残高の0.7%を最大10年間控除 | 初年度の残高が800万円なら、最大で約5万6000円控除(控除額は各年の「年末時点のローン残高」に応じて計算) |
| 投資型減税(特定改修工事に係る特別控除) | 耐震改修工事 省エネ改修工事 バリアフリー改修工事 三世代同居に対応する改修工事 | 工事費の10%(上限あり)を1年で控除 | 工事費120万円なら最大12万円控除 |
| 固定資産税の軽減措置 | 耐震改修工事 省エネ改修工事 バリアフリー改修工事 | 固定資産税が一定期間1/2~1/3軽減 | 固定資産税6万円なら3万円軽減(減額される割合・減額される期間は自治体により異なる) |
住宅ローンを利用する場合(特定増改築等)
住宅ローンを利用してリフォームを行う場合、「特定増改築等住宅借入金等特別控除(住宅ローン型減税)」が適用されます。これは、住宅ローンを組んでリフォーム工事を行った際、年末のローン残高の0.7%を最大10年間、所得税などから控除できる制度です。家計の負担を軽減しつつ、快適な住まいを実現したい方にとって、有効な制度といえるでしょう。
控除を受けるためには、リフォーム費用が100万円を超え、借入金の償還期間が10年以上であることなど、一定の条件を満たす必要があります。
特定のリフォーム工事における所得税の特別控除(投資型減税)
住宅ローンを利用しない場合でも、「投資型減税(特定改修工事に係る特別控除)」を活用できるケースがあります。この制度は、支払った工事費の一定割合を所得税から控除できる仕組みです。
控除率や上限額は工事の内容によって異なります。なお、控除を受けるためには、工事費の合計額が50万円(消費税抜)を超えるなどの要件があります。
リフォーム後の固定資産税の軽減措置
リフォーム後の住宅には、翌年度の固定資産税が一定期間軽減される仕組みも設けられています。所有する固定資産(住宅)に対して課される税金が安くなる制度です。
固定資産税の軽減措置は、自治体への申請が必要です。工事完了から3か月以内など、自治体によって申請期限が異なるため、工事を始める前に市区町村の税務課へ確認しておくことが大切です。
省エネ等住宅は最大1,000万円・一般は500万円の非課税枠
親や祖父母などから新築または取得の援助を受ける場合、贈与税の非課税措置を利用できます。
一定の要件を満たせば、贈与を受けた金額のうち最大1,000万円(省エネ・耐震・バリアフリー改修などの「省エネ等住宅」)までが非課税となります。その他の一般的なリフォームでも、最大500万円までの非課税枠が設けられています。
主な要件
・リフォーム後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
・建築後使用されたことのない住宅用の家屋または建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
また、贈与を受けた翌年に確定申告を行う必要がある点に注意してください。贈与額が非課税枠を超えた場合、その超過分には贈与税が課税されますので、資金計画の段階で慎重に確認することが重要です。
贈与税の非課税(親からの資金援助)で増改築も対象
贈与税の非課税措置は、新築だけでなく増改築やリフォームも対象です。たとえば、子ども世帯が実家をリフォームして同居する場合などにも活用できます。
主な要件
・増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下
・「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること
贈与額が非課税枠を超えた場合、その超過分には贈与税が課税されますので、資金計画の段階でしっかり確認しておくことが重要です。
補助金(住宅省エネ2025キャンペーン)との違い
リフォーム減税と似た支援策として、「住宅省エネ2025キャンペーン」などの補助金制度があります。これらは、省エネ性能の高い住宅リフォームを対象に、国が交付する補助金制度です。
補助金と減税は別の制度であるため、併用も可能です。補助金を受け取った場合、原則としてその補助金額を控除対象となるリフォーム工事費から差し引いて申告する必要があります(※耐震改修工事に係る控除など、一部の例外を除く)。
「補助金をもらったから減税が受けられない」ということではなく、両方を上手に組み合わせることで、実質的な自己負担額を大きく減らすことができるのです。補助金の交付が決定した後、減税の確定申告をする際、この差引き計算を忘れないように注意しましょう。
減税額を最大化するための注意点と併用ルール

リフォーム減税を上手に活用するには、複数の制度の併用ルールや対象工事の線引きを正しく理解しておくことが重要です。ここでは、よくある疑問点と注意事項を整理します。
減税制度の併用はできる?
リフォーム減税制度は、複数の制度を同時に適用できる場合があります。たとえば、以下のような住宅ローンを利用したリフォームで所得税の控除を受けつつ、同じ工事で固定資産税の軽減措置を併用することも可能です。
具体的な工事例は以下のようなケースがあります。
| 住宅ローン型減税+固定資産税の軽減措置 | 老朽化した木造住宅を耐震改修し、住宅ローン(1,000万円・10年返済)を利用。→所得税で最大70万円の控除+固定資産税1/2軽減の併用が可能。 |
| 贈与税の非課税+投資型減税 | 親から500万円を贈与され、省エネリフォーム(費用150万円)を現金で実施。→贈与分は非課税(約50万円節税)+工事費150万円の10%(15万円)控除の両方を適用可能。 |
ただし、同じ工事に対して二重に所得税控除を受けることはできません。また、補助金を受け取った場合は、その金額分を控除対象から差し引いて計算する必要があります。
制度ごとに条件が細かく異なるため、工事を計画する段階で、「どの制度を組み合わせるとお得になるのか」などを専門家に確認しておくと安心です。
控除対象となる工事の線引きと注意点
減税の対象になるかどうかは、工事の内容や目的で決まります。たとえば、「老朽化した壁紙の張り替え」や「外観のデザイン変更」など、美観を目的とした工事は原則として控除対象外です。
一方で、次のような機能向上を目的とする工事は減税の対象となります。
- 耐震性を高める改修工事
- 断熱材の追加や窓の二重サッシ化など、省エネ性能を向上させる工事
- 段差解消や手すり設置などのバリアフリー改修
同じリフォームでも、対象になる部分とならない部分が混在する場合があります。見積もり時に工事項目を明確に分け、申請書類にも正確に記載しておくことが大切です。
減税を適用するための申請方法
リフォーム減税を受けるには、工事完了後に正しい手続きを行う必要があります。ここでは、代表的な申請方法を紹介します。
所得税控除のための確定申告の流れ
リフォームに関する所得税控除は、確定申告で手続きを行います。会社員であっても、自分で申告が必要です。
申告の手順は次の通りです。
- リフォーム工事が完了したら、施工業者から工事証明書や領収書を受け取る
- 住宅ローンを利用した場合は、残高証明書を金融機関から取得
- 確定申告書に必要事項を記入し、上記の書類を添付して税務署に提出
電子申告(e-Tax)を利用すれば、自宅からでもスムーズに手続き可能です。
必須書類の種類
リフォーム減税の申請では、工事内容に応じて提出書類が異なります。
主な書類は以下の通りです。
- 工事証明書(施工業者が発行)
- 領収書や契約書の写し
- 住宅ローンの残高証明書(ローン利用時)
- 登記事項証明書(住宅の所有者確認用)
- 確認申請書や検査済証など(必要に応じて)
書類の不備があると控除が受けられない場合があります。工事前から必要書類をリストアップし、漏れなく保管しておくことが重要です。
固定資産税の軽減を受ける方法
固定資産税の軽減を受ける場合は、自治体への申請が必要です。申請期限は、工事完了から3か月以内、または翌年の1月31日までなど、自治体によって異なります。
申請の際に提出する書類は次の通りです。
- 工事証明書
- 領収書
- 建築士または指定確認検査機関による証明書
- 改修工事後の写真
自治体によって様式が異なるため、事前に市区町村のホームページで最新情報を確認しておくと安心です。
リフォームの検討段階で知っておきたい相談窓口

リフォーム工事が初めての方にとって、減税制度は複雑に感じるかもしれません。相談窓口を上手に活用し、計画段階で相談しておくことで、手続きがスムーズに進みます。
リフォーム業者への相談
まずは、リフォーム業者に相談するのが第一歩です。補助金や減税制度に詳しい業者であれば、どの工事が対象になるか、申請の流れまで具体的に教えてくれます。見積もり段階で「減税対象の工事を含めたい」と伝えておくと、工事項目を正確に分けた提案がもらえるでしょう。
税制に関する専門家(税理士など)への相談
税金の控除や併用ルールについて詳しく知りたい場合は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。特に、複数の制度を併用する場合や、親からの資金援助を受けるケースでは申告内容が複雑になります。専門家のサポートを受ければ、誤りのない手続きができ、結果として控除を最大限に活用できます。
よくある質問

Q:一括払いのリフォームは、住宅ローン減税を受けられない?
A:住宅ローン減税は10年以上のローンを組んだ場合のみ対象です。一括払いでリフォームを行う場合は、住宅ローン型減税ではなく、投資型減税(特定改修工事に係る特別控除)の対象になる可能性があります。
Q:固定資産税の減額は併用できる?
A:所得税の控除とは併用可能です。ただし、同じ工事内容で複数の所得税控除を同時に申請することはできません。申請時には、それぞれの制度の対象範囲を確認しておきましょう。
Q:中古住宅を購入してリフォームした場合も対象になる?
A:中古住宅でも、一定の条件を満たせばリフォーム減税の対象です。住宅ローン控除の場合、築年数や耐震基準などに制限があるため、購入前に条件を確認することが重要です。
まとめ
リフォーム減税は、多額の住宅ローンを組む場合も、自己資金で一括払いをする場合も、それぞれに応じた所得税控除が用意されているのが特徴です。
また、この制度の最大の利点は、補助金や固定資産税の軽減措置と組み合わせて使える点にあります。これらを活用することで、節税効果を最大限に引き出し、経済的なメリットが得られるでしょう。
しかし、制度ごとに条件や期限、提出書類が細かく異なっている点に注意が必要です。リフォームを始める前には必ず最新の情報を確認してください。信頼できるリフォーム業者に相談し、この制度を賢く利用しながら、安心で快適な住まいを実現しましょう。